おせちの「数の子」の意味は、ニシンの小さな粒々の卵がたくさん集まっている形状から「子だくさん」や「子孫繁栄」を表しています。
また、おせちの数の子の黄金色が縁起物を意味しているとも言われてます。
今回は、そんな数の子の歴史をたどりながら、おせちの数の子の意味や由来をご紹介し、数の子の”塩抜き方法”についてもレクチャーさせていただくので、ぜひチェックしてみてください♩

目次
みなさんは、おせちに入る食材で一番先に思い浮かぶものは何ですか?私は、まず「数の子」を思い浮かべてしまいます。
なぜなら、私にとって「数の子」は、栗きんとん・蒲鉾・黒豆と並ぶおせちの定番だからです!これが入ってないと、なんとなく寂しい気持ちになるのは私だけでしょうか?
おせちのお重のフタを開けた瞬間、思わず眩しい黄金色を放つ「数の子」に、つい目がいってしまいます。それで印象に強く残っているのかもしれませんね!
「数の子」は、その華やかな色や姿から、お祝い事にはとてもふさわしい「祝い肴」の一つとされるため、お重の一番上にある”一番重”に詰められます。
という訳で、早速本題に移りたいと思います!
数の子の名前の由来は?

では、なぜ「数の子」と呼ばれているか、みなさんはご存知ですか?
私も知らなかったのですが、昔はニシンのことを「カド」と呼んでいたそうです。
つまり、ニシンの子である数の子は「カドの子」、その名前が徐々に変化して、今の「数の子」になったという説があるようです。
数の子がおせちに入る、意味・由来は?

「数の子」はお魚の”ニシンの卵”です。小さな粒々の卵がたくさん集まってできていることから、おせちの一品として「子だくさん」や「子孫繁栄」を祈る意味があります。この由来の歴史は古く、なんと室町時代から言われていたという説もあるのだとか。
また、”ニシン”を”二親”とかけて、両親からたくさん子供が生まれることを願うという意味もあるそうです!
卵がたくさんあるという由来で”子孫繁栄”であることは聞いたことがありましたが、「二親」の由来の話は初耳でした……。思わず、手を叩いて納得してしまいました!!
また、最初にも書きましたが、その”黄金色”から縁起物を表す意味もあるみたいです!独り身である私は、どちらかというとこちらの由来にあやかりたいものです……。
数の子の歴史

「数の子」は、14世紀頃に北海道から京都に伝わったという説があります。
ところが、はじめは数の子単独で食べられていたわけではなかったようです。当時は、北海道から京都への納品は”昆布”が主だったようで、その中に、昆布にニシンが卵を産み付けた「子持ち昆布」が含まれていたそうです。
そこから、ニシンの卵である数の子が評価されはじめ、数の子が単独で縁起物として広まっていったという説もあります。
ちなみに、ニシン自体が一般的に食べられるようになったのは、明治時代になってからと言われています。
数の子は高級品!?

「数の子」の親となるニシンは、昭和の初期までは多くの漁獲量を誇っていたようですが、昭和30年代以降、乱獲などにより急激に漁獲量が減ってしまったそうです。
そのため、それ以来、数の子の価格も高騰していき、国産の数の子は高級なイメージが付いてしまいました。そこから、カナダ産やアメリカ産など海外の数の子も広く出回るようになったようです。
海外産「数の子」のあれこれ

評価が高いとされるカナダ産やアメリカ産の「数の子」ですが、水揚げ場所が太平洋側(西海岸側)か大西洋側(東海岸側)かで、評価が大きく異なります。一般的には太平洋側の方が食感も良く、評価が高いとされています。
カナダ産とアメリカ産の違いは”数の子の大きさ”です。
アメリカ産の方がやや大ぶりと言われています。ただし、大きい方が優れているというわけではなく、関西地方などでは小ぶりなカナダ産が好まれる傾向もあるんです。
とっておきやのおせちには、カナダ産の数の子を使用しています。カナダ産の数の子は、形と食感が良く高級品とされています。
カナダ西海岸にあるバンクーバー島周辺の海域は、ニシンの漁場でそこでとられた数の子のほとんどが日本へ輸出されているそうです。毎年産卵のために来遊するニシン。卵が完熟になるのを待って、漁業がスタートします。その漁獲期間や量は、カナダ漁業海洋省によって規定されているそうです!
数の子は漁獲量が安定しないため、毎年価格が高騰しているのが現状です。これからは国産のものだけでなく、世界的に数の子は「高嶺の花」になってしまうかもしれませんね……。
市販の”数の子の種類”について

「数の子」には、”味付け数の子”、”干し数の子”、”塩数の子”の3つのいずれかの形態で市販されているケースがほとんどです。
弊社のおせちに入っている数の子は、”味付け数の子”です。
醤油ベースに昆布エキスなどを使用することで、香り高く、上品な味に仕上げています。”そのまま食べられる”のも味付け数の子の特長です。
▼ちなみに、弊社自慢の数の子は、こちらのHPより詳しい商品情報を見ることができるので、よろしければご覧ください。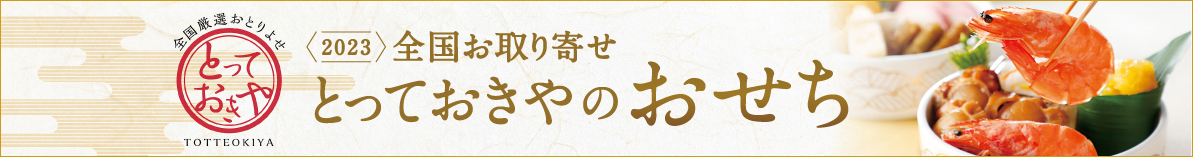
▼また、弊社おせちの数の子を作っていただいている”メーカー様への探訪記”の記事もございますので、ぜひチェックしてみてください!
https://www.osechiya.aussie-fan.co.jp/osechi/blog/429/
一方、市販されている数の子はほとんどが”塩数の子”です。
塩抜きの作業が少し大変ですが、ご家庭でお好みの味付けをしたり、さまざまなお料理にアレンジすることも可能です。
干し数の子と塩数の子の違い
”干し数の子”は、天日干しされた数の子で、かちかちに固くなるまで干されています。今では希少品ですが、冷蔵庫がなかった時代には「干し数の子」が一般的でした。
食べるときには、水か米のとぎ汁に2~3日つけて戻します。手間がかかり、製造コストも高いため、現在は見かけることがほとんどなくなりました。
”塩数の子”は、塩漬けされた数の子です。20時間程度水に浸けて塩抜きをしてから食べます。“干し数の子”に比べて、安価で調理がしやすいため、現在は“塩数の子”が選ばれることが多いです。。
数の子の塩抜き方法
- ① 数の子を大量の水に20時間程付ける。(途中で2~3回水を取り替えます)
- ② 数の子の表面の薄い白皮を取り除く。
- ③ 表面の水分をペーパータオルなどでふき取る。
以上の工程だけで塩抜きができるのですが、もっと時間を短縮したい方は、1.の工程で水に食塩を少々(水500mlに対し塩5g程度)入れると半分程度の時間、さらに水を流し放しておくともっと早い時間で済むそうですよ。
また、塩を抜きすぎると”苦み”を感じる場合があるので、塩味がほんのり残る程度がいいようです。
ぜひ、ご家庭で試してみてくださいね!
数の子の新たな一面に出会う

いかがでしたでしょうか?数の子ひとつとっても、様々な話題があるものですね!
私もこのブログを書く前は意味や由来しか書くことはなさそうだって思ってのですが、いざ書き出すと、私自身、数の子に対する”新たな発見”があり、とても楽しく書くことができました。みなさんとも、そんな気持ちを共有できたら幸いです!
嶋添
最新記事 by 嶋添 (全て見る)
- 「金のおせち 2023年」お客様の声いただきました! - 2023/02/17
- ローストビーフ~おせちやスタッフが行く産地訪問記!岩手県 - 2021/09/04
- 数の子がおせちに入る意味・由来は?その歴史に迫る! - 2021/07/30





