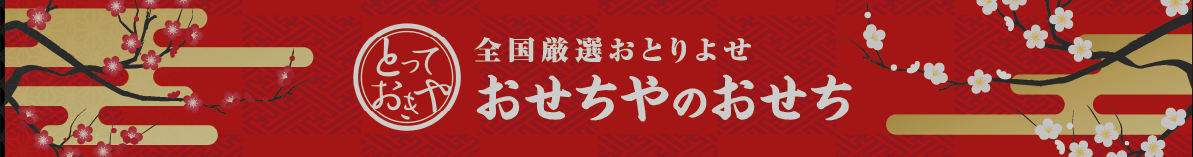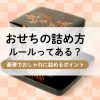「おせち定番の中身」と言えば、黒豆・数の子・田作り・伊達巻など、さまざまな料理があります。それぞれに良い意味やいわれがあり、縁起物として新年に願いを込めて食べられてきました。
今回は、そんなおせち定番の中身の種類・意味・由来・詰め方まで、徹底的にレクチャーいたします!
来年のおせち料理の準備にお役立ちできたら嬉しいです。
目次
おせち定番の中身を構成するのはこの4つ!

そもそも「おせち料理」は、正月に食べるお祝い料理のことで、漢字で「御節(おせち)」と書きます。御節とは、季節の節目である「節(せち)」を意味しています。
その時の収穫物の報告や感謝の意味を込めて、その土地でとれた季節の野菜などを年神様にお供えしていたことが「おせち料理」の起源です。
その後、時代をの経過とともに食文化が発達し、料理は豪華になり、今のおせち料理の原型へとつながりました。
おせち定番の中身は、基本的に下記の4つの構成が必要不可欠とされています。
- 祝い肴(一の重)
- 焼き肴(二の重)
- 酢の物(三の重)
- 煮物(与の重)
おせち料理は「めでたい」を重ねるため、重箱に詰められます。その中身は、一般的に20~30種類作ることが多いです。
地域によって中身の食材は異なりますが、重箱の定番の中身の構成を解説していきます。
祝い肴
一の重の「祝い肴」は、お正月を祝うために欠かせない3種類の料理で「三つ肴」「三種肴」とも呼ばれます。
「不老長寿」「子孫繁栄」「家内安全」などの意味が込められています。三段重の場合も、五段重の場合も、一番上の「一の重」に入れます。
中身は地域や風習によって異なりますが、一般的な違いは以下の通りです。
【関東の祝い肴】
- 黒豆
- 数の子
- 田作り(ごまめ)
【関西の祝い肴】
- 黒豆
- 数の子
- たたきごぼう
焼き物
二の重の「焼き物」は、炭火などで焼いた料理で、鯛・ブリ・海老・貝類などの縁起が良い、海の幸を入れます。
「鯛の姿焼き」「鯛の西京焼き」「ブリの照り焼き」「ブリの塩焼き」「車海老の西京焼き」「帆立貝の黄金焼き」など、さまざまな料理があります。
三段重の場合はニの重、五段重の場合は三の重に詰めるのが一般的です。
酢の物
三の重の「酢の物」は、日持ちするのでおせち料理には欠かせない料理です。肉や魚料理が多いおせち料理の中で、「野菜が摂れる」という意味でも重宝されます。
「紅白なます」や「酢れんこん」などが一般的ですが、大根、にんじんに加え、きゅうり、しいたけ、油揚げなどを加えた「五色なます」、干し柿や生の柿を入れた「柿なます」、鮭の頭部の軟骨を酢締めにした「氷頭(ひず)なます」、皮つきの白いクジラの脂身を加えた「くじらなます」などもあり、酢の物には地域の特色があらわれています。
三段重でも五段重でも、二の重に詰めるが一般的です。
煮物
与の重の「煮物」は、様々な食材を一緒に煮ることから「家族が仲良く、一緒に結ばれ、末長く繁栄するように」という意味が込められています。
「筑前煮」「煮しめ」とも呼ばれ、その違いは調理法にあります。具材を煮る前に油で炒めるのが筑前煮、具材ををじっくりと時間をかけて煮汁を染み込ませていくのが煮しめです。
それぞれの食材にも一つ一つ意味が込められており、三段重の場合は三の重、五段重の場合は与の重に詰めます。
筑前煮と煮しめの違いは、こちらの記事で詳しく解説しています↓
おせち中身の定番の品目数は「奇数」

おせち料理の中身は、基本的に「奇数」の品目数で詰められることが多いです。
これは、日本では昔から“奇数の方が縁起が良い”とされてきたことに由来しています。各家庭にもよりますが、だいたい20~30種類程度となっています。
奇数が縁起が良いとされる理由は、長い歴史の中で諸説あるようです。
例えば「偶数は2で割れてしまう=別れてしまう」から奇数の方が縁起が良い説。
また「陰陽道」の考え方で「奇数は『陽の数字』で、偶数が『陰の数字』である」という説。
などなど、様々な説が元になっています。
ちなみに、弊社オージーフーズの「金のおせち」は、こだわり詰まった18種類をお届けしています!
全国各地の美味しい食材を厳選してお取り寄せしている自慢のおせち。よろしければ、ぜひ下記の弊社HPをご覧ください。
また、おせち料理の全般的な意味や由来のお話にご興味がある方はこちらのブログ記事がおすすめです!↓
おせち定番の中身の種類・意味・由来
次は、おせち定番の中身の種類について、それぞれ詳しく解説します。その食材に込められた意味・由来、おすすめの盛り付け方のワンポイントアドバイスもご紹介しますよ♪
また、それぞれの食材ごとに、さらに詳しい情報に迫ったブログ記事もございますので、あわせてチェックしてみてくださいね♩
定番おせち①蒲鉾(かまぼこ)

蒲鉾(かまぼこ)は、板に半月型に整えられていることから、その形が“日の出”を表すとされ、「新しい門出」を象徴するといわれています。
また、おせちには紅白の蒲鉾が入れられていることが多いですが、その色の意味は、「赤=魔除け」「白=清浄」だそうです!どちらの色もおめでたい!
上記の様々な要因によって、蒲鉾が縁起の良い食べ物と重宝され、おせちに入れられるようになったという訳なのです。
ちなみに、盛り付ける時は紅白交互に並べて詰めるとお互いの色が引き立ちあうのでオススメですよ。
蒲鉾について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ↓
定番おせち②伊達巻

伊達巻って“巻き物(書物)”に形が似ていると思いませんか?
そのことが由来して、「知識が増える」ことを願う縁起物とされているんです。そのため、学問の成就の意味が込められています!
盛り付けのコツは、伊達巻の中心の巻き目が「の」の字になるように並べるのがオススメです。
実は伊達巻には他にも意味が込められています。伊達巻について知りたい方は下記の記事をご覧くださいませ。スタッフが伊達巻作りに挑戦してみたお話しも必見ですよ↓
定番おせち③黒豆

おせち料理の中で、黒豆には3つの願いが込められています。
- “まめ”によく働く=「一年間健康でいられますように」
- 黒は「魔除け色」とされている=厄除けの意味
- 黒豆のふっくらとハリのあるその容貌=「シワが寄らず、長生きできますように」
確かに、ふっくらとした艶とハリのある黒豆のような肌、特に女性にとってはいくつになっても憧れですよね~♩
盛り付ける時は、お重箱の中でこぼれないように小鉢などに詰めると良いですよ。
黒豆についてより詳しい情報はこちらの記事をどうぞ!↓
定番おせち④酢れんこん

れんこんは、輪切りにすると複数の穴が開いていて、その先をのぞくことができますよね。このことから、「見通しがきく」、「将来を明るく見通せる」とされています。
また、れんこんは種が多いことから「子孫繁栄」の意味を持っているのだとか。
ちなみに、蓮の花が「最も極楽浄土にふさわしい花」と言われていることは知っていましたか?そのため、そういった意味でも縁起の良さが感じられますよね。
酢れんこんを盛り付けるなら、この意味が伝わるように「穴」が見えるように並べてみてはいかがでしょうか♩
れんこんのもっと深~いお話しはこちらの記事をご覧くださいませ↓
定番おせち⑤栗きんとん

栗きんとんには、縁起の良さを表す2つの意味があります。
- 「勝負運」を願った意味が込められている。
- 「商売繁盛や金運をもたらす縁起物」とされている。
両方の意味も新年にもってこいですね!
盛り付ける時は、栗きんとんの餡が他の食材にくっつかないように小鉢などに詰めてからお重箱に並べるのがオススメです。
おせち料理の中でも、お子様人気の高い一品です。もっと詳しいこちらの記事をお読みいただいて、ぜひ来年のお正月には栗きんとんのお話しをしてあげてくださいませ↓
定番おせち⑥田作り

田作りは、決して目立つ存在ではないですが、関東では「祝い肴」の一つに入っています!
そんな田作りが、おせちに入っている縁起の良い意味は3つあります。
- 豊作
- 健康
- 子孫繁栄
田作りを盛り付ける時は、頭の方向が揃うように並べるとキレイです。
それぞれの意味の由来について詳しくはこちらの記事をご参照ください。スタッフが作ってみた、おしゃれな「田作りアレンジレシピ」も必見です!↓
定番おせち⑦たたきごぼう

たたきごぼうには、縁起の良い意味がたくさんあることをご存知でしたか?
大きく分けて、4つの意味があります。
- 「豊作」の願いが込められている。
- 「家や家業が地に根付き安定する」願いが込められている。
- 「新年の健康・延命長寿」の願いが込められている。
- 「新年の開運」への願いが込められている。
たたきごぼうについて、より詳しいお話しはこちらの記事にてご紹介しております↓
定番おせち⑧紅白なます

紅白なますは、紅白の色から「水引」を表すとされ、縁起物として重宝されています。
また、根菜のように“根を張るように”という願いが込められているのだとか。
詳細はこちらの記事もチェック!↓
定番おせち⑨昆布巻き

昆布巻きは、昔「ひろめ」と呼ばれていて、その幅の広い形状から「広布」と表されていました。それが「こんぶ」と音読みがされたことが始まりだったとされています。
また、「よろこぶ」に通ずるとされており、縁起が良いものとして重宝されています。
結婚式の「お披露目(おひろめ)」も、この「ひろめ」からきているのだとか…。
ちなみに、当店のおせちの昆布巻きは、中心ににしんが詰められた「にしんの昆布巻」です。真ん中のにしんが見えるように、縦に立てて並べるのがオススメです!↓
定番おせち⑩数の子

数の子は、「子孫繁栄」を祈る意味が込められています。
また、その“黄金色”も縁起物とされている理由の一つです!
確かに、黄金色の食材はなかなか見ないので、それだけで縁起のよさと高級感を感じます。
当店のおせちの数の子は形を維持して「一本羽」を×3本ご用意しております。
盛り付ける時は豪快に、そのままの形を活かしてお重箱から少しはみ出るくらいに盛り付けてみてはいかがでしょうか♩↓
定番おせち⑪海老

海老は、調理をするとクネっと「つ」の字のように曲がってきますよね。それに由来して、「腰が曲がるまで長生きしますように」という願いが込められているのだそう。
盛り付ける時も、その意味を込めて「つ」の字に並べましょう。
また、脱皮を繰り返して大人になる海老の特性に由来し、「出世」を願う意味もあるみたいですよ!
「海老」の意味や調理方法は、こちらの記事をチェックしてください↓
定番おせち⑫煮物・筑前煮・お煮しめ

煮物は、上記で紹介したれんこん、ごぼう、などの縁起物に加え、里芋、こんにゃく、椎茸など、「子孫繁栄」や「末永い幸福」を願う食材がたくさん入っている、とても縁起の良い料理です♩
詳しい意味や由来のお話などは、こちらの記事をご覧ください。
「金のおせち」と「数寄のおせち」に入るおせちのいわれはこちら↓
| 商品名 | 量 | 金 | 数寄 | いわれ |
| 宇部の手巻蒲鉾「新川」(白) | 1本 | 〇 | 〇 | 蒲鉾の切り口が日の出を表す。新しい門出を象徴。 |
| 伊達巻(烏骨鶏卵使用) | 200g | 〇 | 〇 | 巻き物に形が似ていることから、知恵が増える縁起物。 |
| 紅白なます(昆布入り) | 100g | 〇 | 〇 | 紅白の水引。人と人が結ばれる。根菜のように値を張る。 |
| 味付数の子(※カナダ産) | 60g(3本) | 〇 | 〇 | 魚卵で子孫繁栄。金色がめでたい。 |
| 若桃の甘露煮 | 5粒(Mサイズ) | 〇 | 〇 | 桃は邪気を払う。長寿の象徴。 |
| 白姫海老の旨煮 | 4尾(Mサイズ) | 〇 | 〇 | 腰が曲がるまで長生きできるように。 |
| にしん昆布巻 | 1本(85g) | 〇 | 〇 | 昆布=「よろこんぶ」。 |
| 田作くるみ | 22g | 〇 | 〇 | 田を作る。豊作祈願。 |
| 栗きんとん(栗あん&いもあん) | 130g(栗4個) | 〇 | 〇 | 金色から商売繁盛や金運をもたらす縁起物。勝ち栗ともいう。 |
| いくらの醤油漬 | 80g | 〇 | 〇 | 日の丸のように赤く丸い。めでたい。 |
| 国産竹の子土佐煮(穂先) | 5個入 | 〇 | 〇 | 成長が早い縁起物。 |
| 焼き帆立(4L) | 5粒 | 〇 | 〇 | 帆立貝の漢字から順風満帆。 |
| 鮑(あわび)煮貝 ※チリ産 | 1粒(60g) | 〇 | 〇 | 鮑は長生き。不老長寿を願う。 |
| 丹波篠山産黒大豆 | 200g(固形量2Lサイズ80g) | 〇 | 〇 | まめによく働き元気に暮らす。 |
| 国産和牛ローストビーフ | ローストビーフ100g、ソース10g付 | 〇 | 〇 | 新年から美味しい。 |
| たたきごぼう | 40g | 〇 | 〇 | 豊作を願う。 |
| にしん旨酢漬け(新商品) | 60g | 〇 | 〇 | 二親から両親健在。子宝祈願。 |
| 国産豚のローストポーク(新商品) | 135g | 〇 | 新年から美味しいものを食べて健やかに。 | |
| 鴨ローススモーク(スライス) | 70g | 〇 | 鴨は「こうのとり」と読め、子宝に恵まれる。 | |
| からすみスライス(新商品) | 4枚 | 〇 | ぼらは出世魚。出世を祈う。 | |
| 紅鮭スモークサーモン | 50g | 〇 | 災難を避け、大きくなって戻ってくる。 | |
| 日光 味付ゆば(新商品) | 4個 | 〇 | ゆばは体によい。健康長寿。 | |
| 味付京生麩 | よもぎ3枚+梅2枚 | 〇 | よもぎは生命力がある。縁起の良い紅い梅麩入り。 | |
| 気仙沼産ふかひれ姿煮(背びれ) | 160g (固形量50g) | 〇 | 新年から美味しいものを食べて健やかに。 | |
| 金箔 | 〇 | 〇 |
おせちの定番!重箱の基本の詰め方

おせちの重箱は「幸せ・めでたさが積み重なりますように」という思いが込められており、「めでたさを重ねる」という意味もあります。
かつて重箱は、“五段重”が定番でした。しかし、近年では一段重なども誕生し、様々な形のおせち料理へと変化しています。
おせちは、料理が華やかに見えるよう、彩りを考えて重箱に詰めていくことがポイントです。ここでは、「五段重」「三段重」の基本の詰め方をご紹介していきます。
五段重の詰め方
まずはじめに、従来から定番とされている「五の重」の詰め方についてご紹介します!
五段重|一の重
「一の重」には、“祝い肴”を詰めます。
- 数の子
- 黒豆
- 田作り
- たたきごぼう
など
五段重|二の重
「二の重」には、“酢の物・口取り”を詰めます。
- 伊達巻卵
- 蒲鉾
- 栗きんとん
- 布巻き
- 酢れんこん
- 紅白なます
など
五段重|三の重
「三の重」には、“焼き物”を詰めます。
- 海老
- 鯛やブリなどの焼き魚
など
五段重|与の重
「与の重」には、“煮物”を詰めます。
- 筑前煮
- お煮しめ
など
五段重|五の重
五の重は何が入るのかというと……なんと「空」なんです!「なぜ“空”なの?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか?
もちろん、ちゃんとした意味があるんです!
その意味はというと、五の重は古くから“年神様から授かる「福」を詰める場所”とされているため、何も詰めないでおくか、または家族の好物などを詰めるのが良いといわれています。
ちなみに、四段重の場合は、「五段重」の「五の重」をなくした詰め方で作るのが良いそうです!
三段重の詰め方

近年は二~三段重のものが増えてきています。ここでは「三段重」の詰め方もご紹介いたします。
三段重|一の重
三段重の場合、「一の重」には“祝い肴”と“口取り”を詰めます。
- 数の子
- 黒豆
- 田作り
- たたきごぼう
- 伊達巻卵
- 蒲鉾
- 栗きんとん
- 昆布巻き
など
三段重|二の重
三段重の場合、「二の重」には“酢の物”と“焼き物”を詰めます。
- 酢れんこん
- 紅白なます
- 海老
- 鯛やブリなどの焼き魚
など
三段重|三の重
三段重の場合、「三の重」には“煮物”を詰めます。
- 筑前煮
- お煮しめ
など
おせちの詰め方は、こちらの記事でも詳しく解説しています!↓
まとめ|おせちの定番の豆知識はこれで完璧!

いかがでしたか?
今回は、おせち料理の定番の中身とされる食材を中心に、それぞれに込められた思い、そして重箱についてをご紹介しました。
ぜひ、ご家庭でのおせち作りやおせち選びの参考にしてみてくださいね♪
これからも「おせち」という食文化について、もっともっと詳しくご紹介していきます。
今後とも株式会社オージーフーズが運営するおせちの達人「おせちや」をどうぞよろしくお願いいたします。
また、弊社では”おせち専用インスタグラム”を始めました!
おせちについてのあれこれをインスタグラムで簡単にチェックできるので、よろしければぜひご覧ください!
最新記事 by おせちの達人「おせちや」 (全て見る)
- たけのこの茹で方と下処理方法【おせち手作り派の方におすすめ】 - 2024/04/25
- 水上食品様の栗きんとんの魅力に迫る【おせち食材産地訪問動画】 - 2024/04/25
- おせち料理の盛り付け方のコツ【お皿盛り編】解説動画 - 2024/04/25